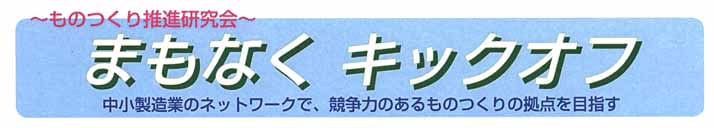
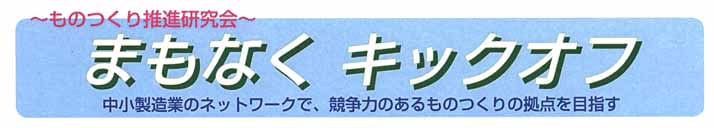
地域経済や中小企業の足元は、かつてない深刻な状況にある。その状況を脱却するには、優秀な技能・技術を維持し、いかに次世代に継承していくか、そして、従来の技能・技術にIT(情報技術)、ハイテク技術を組み合わせ、新たな製品開発ができるような創造的技能・技術者の育成・確保がポイントである。
本所では、中小製造業における技能、技術の維持・継承・高度化等の活動を行うため「ものつくり推進研究会」をスタートさせる。
今回、産業活性化委員会で3年間に及ぶ「ものつくり」の研究に携わっていただいた産業活性化委員会
委員長である田口竜也 氏(株式会社三龍社 代表取締役社長)と「ものつくり推進研究会」の提案者である中村重嗣
氏(中村科学工業株式会社 代表取締役社長)より、ものつくり産業の現状とこれから活動する「ものつくり推進研究会」についてお聞きした。
 株式会社三龍社 代表取締役社長 |
(中)そうですね。とくに、大企業が生産拠点をアジア地域に移すことで、それに関連する企業までもが、海外に移転せざるを得ない状況となってしまい、これによって国内では産業の空洞化の現象をもたらしています。産業の空洞化は、国内における雇用確保の機会が減少してしまうことと、今まで日本で培われてきた独自の技能・技術までもが海外に流出してしまっている可能性があるということです。
(中)私の考えとしては、今まで行ってきた技能・技術の維持・継承と、もう1つ別の切り口で、IT、ハイテク技術をうまく活用した新しい技能者像を探さなくてはならないと思っています。 |
(中)先程、空洞化の話しをいたしましたが、それに加えて、製造業を支えている熟練技能者が、ちょうど定年退職を迎える時期でもあります。そして、若者の3K職離れ、製造業離れ等の問題が重なりあい、技能・技術の維持・継承がしにくい環境にあると思います。
(田)当たり前のことですが、ものつくり産業は製造現場こそが、企業経営の生命線になります。従いまして、技能・技術の維持・継承を考えた場合、製造現場で働く方々に対して働きやすい環境を整えることが重要かと思います。 (中)ものつくり産業では、やはり「人」がキーポイントとなります。今後、製造現場で働く方が働きやすい環境を整えること。製造業の立役者的存在である技能者・技術者の皆さんが、周りから脚光を浴びることができるような仕掛けづくりを行って、若者にものつくりの大切さを伝えていく必要があると思います。 |
 中村重嗣 氏 中村科学工業株式会社 代表取締役社長 |
| Q.そこで「ものつくり推進研究会」がスタートするわけですが、その活動についてお教えください。 |
(田)ものつくりといっても、業種が多岐にわたりますので、まず立ちあげの段階で、岡崎商工会議所の機械金属部会、工業部会の2つの部会を中心に活動を展開し、成功事例を作っていきたいと考えています。
(田)研究会は、技能・技術部門の責任者を中心に会を構成し、いま岡崎の製造業が抱えている課題解決の場としていきたい。研究会の皆さんが中心となって問題提起をいただきながら、意見交換会やセミナーなど、それに基づいた研究活動を展開していきたいと思います。
(田)また、中部経済産業局では、産業クラスター計画の一つとして、昨年度から「東海ものづくり創生プロジェクト」の事業を推進しています。このプロジェクトは、産学官の広域的な人的ネットワークを形成し、産業集積を創生することを目的としています。我々が計画している「ものつくり推進研究会」の活動と重なる部分がありますので、こうした国の動きとも連携を図りながら、事業を進めていきたいと考えています。
| Q.どうもありがとうございます。 |
(田)次ページに「ものつくり推進研究会」の具体的な活動を示しますので、ご覧ください。
5月28日(火)午後1時〜3時30分「ものつくり推進研究会」キックオフセミナーを開催いたします。ぜひご参加いただきますようお願いします。まもなくキックオフ。